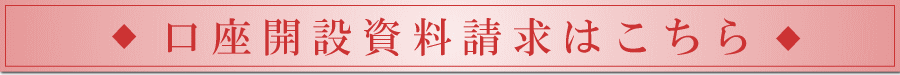光世証券ホーム > ザ・対談 第1回
光世証券ホーム > ザ・対談 第1回

知れば安心、使えばお得。 個人投資家にこそお勧めしたい “デリバティブ”の効能。
【前編】難しい?危ない!? その先入観がもったいない!!
光世証券株式会社 社長 巽 大介
株式会社東京証券取引所 常務取締役 土本清幸
(聞き手: みんかぶ 小松俊一)

- たつみ だいすけ
1964年5月17日生。大阪府出身。
慶應義塾大学経済学部卒業後、野村證券(株)を経て、1997年、光世証券(株)に入社。理事・社長室長、取締役を歴任し、2000年6月、代表取締役社長に就任。

- つちもと きよゆき
1959年11月19日生。愛知県出身。
慶應義塾大学経済学部卒業後、東京証券取引所に入所。秘書役、上場部長、常務執行役員、常任理事を歴任し、2013年6月、(株)東京証券取引所常務取締役に就任。
【前編】難しい? 危ない!? その先入観がもったいない!!
「現物の東」と「デリバティブの西」
相乗効果で強くなる。
――巽社長が率いる光世証券は、デリバティブ(金融派生商品)への積極姿勢でよく知られています。その皮切りは1987(昭和62)年、大阪証券取引所が導入した国内最初のデリバティブ商品『株先50』への取り組み。以来、今日まで継続的にデリバティブを推進されて、2011(平成23)年には、東京証券取引所のデリバティブ商品すべてをネットで取り扱える国内唯一の証券会社となるに到っておられます。
ところで、なぜデリバティブなのでしょうか?
 巽 土本常務とお話させていただくにあたり、まず申し上げておきたいのは、この度の大証・東証の統合に対する期待です。
巽 土本常務とお話させていただくにあたり、まず申し上げておきたいのは、この度の大証・東証の統合に対する期待です。
ご承知のとおり私ども光世証券は、創業から大阪に根を張りながらも、「世界に通用する証券会社に」をスローガンにやってきました。金融・証券の分野では、デリバティブ抜きには世界を語ることはできません。証券取引所もそう。“世界の取引所”というのは、「デリバティブに強い取引所」のことを言うんです。
日本は、たとえば工業技術の面では、今も世界の中で飛び抜けた存在感を示しているわけです。しかし、金融面ではどうでしょう。「日本の銀行の普通預金に置いておくのが、実は地球上でパフォーマンスの最も高い運用のひとつだった」なんて言われた時期もあったわけですが、これは、ここ数年の株式低迷に対する皮肉ですからね。
こういうことになった理由のひとつに、デリバティブの遅れがあると私は考えています。デリバティブは、現物と並ぶ“車の両輪”。これが世界の常識です。ならば、世界に伍していくためには、デリバティブで力を付けることが何としても必要でしょう。
今年は、先進各国が変動相場制に移行して40周年。その佳節に、デリバティブに強い大証と、現物取引では有数の東証が、満を持して統合した。
日本の証券市場も、ようやく“世界”が見えてきた、ということでしょうか。
土本 株式会社東京証券取引所グループ(東証グループ)と株式会社大阪証券取引所(大証)は、この今年の1月1日付けで合併し、「日本取引所グループ」(JPX)として新たな歩みを開始いたしました。
巽社長が指摘されたとおり、“デリバティブの強化”は、統合によって得られるシナジー効果の重要なひとつと考えています。
実は、統合をする以前から、東証ではここ数年一貫してデリバティブ市場の強化を目標として掲げてきました。これは、昨今、デリバティブ市場の強さが取引所としての価値を左右する時代になってきているためです。
デリバティブは、日本語で“派生商品”と言うように、株式などの現物から派生して取引される商品です。いわば「現物あってのデリバティブ商品」なのですが、デリバティブ市場がきちんと整備されていて、かつ流動性が備わっていれば、投資家は、デリバティブ市場をリスクヘッジに利用しながら、現物市場にも参入しやすくなります。すると、現物市場もさらに盛り上がってくるわけです。このように、現物市場とデリバティブ市場は、まさに車の両輪と言える関係にあります。
そのような意味で、株式などの現物市場に強みを持つ東証と、デリバティブを長く得意分野としてきた大証が統合したことで、投資家の皆様にとっても利便性の向上につながるはずですし、取引所として、世界と競争していく力が増したと思っております。
巽 私に言わせれば、こと金融に関しては、日本では西高東低というのか、西のほうがまだしも先進的ですね。
デリバティブへの取り組みも東証より大証のほうが早かった。株式公開も大証が先。
土本 ......これは手厳しい(笑)
巽 あくまで私見ですが、日本では、新しいアイデアは常に西から生まれ、東によって廃されてきた歴史があるんです。そもそも大阪は、実はデリバティブの“発祥地”です。1730(享保15)年に江戸幕府の公認で開設された「堂島米会所」が、世界最初の先物取引市場なんですよ。
これは世界で広く知られた歴史的事実。たとえば“先物の父”と呼ばれるレオ・メラメド氏(米国シカゴ・マーカンタイル取引所グループ名誉会長)なども、「堂島米会所こそ先物の故郷である」とはっきりと認めています。
ところが、大坂商人が作った「堂島米会所」も、明治維新のとき、新政府=東京の都合によって廃止されてしまった。
“デリバティブ発祥の地”で奮闘してきた立場としては、大証・東証が統合したJPXには、今度こそ、うまくいっていただかないと困るんです(笑)。
「損をしない」ための仕組みであり、
「利益を極大化する」ためのツールである。
――多くの個人投資家にとって、デリバティブには「敷居が高い」というイメージがありますが……。
巽 一口に金融商品といっても、本来は実に多彩なわけです。それこそ、金融市場には現物、先物があり、オプション市場があって、それぞれに裁定が効いている。バリエーションは豊富なのに、日本では、「貯蓄から投資へ」の掛け声も手伝ってか、現在は、信用取引だけが異様なほどに発達しています。これは、少々いびつな形ですね。
その上、一部の取引業者の不心得な行状が繰り返し伝えられてきたことも重なり、今ではすっかり「デリバティブは危ない」「個人投資家には難しすぎる」という負のイメージが醸成されてしまいました。実に嘆かわしいことです。
土本 本来、デリバティブとは、個人投資家にこそ、有効に活用していただきたい商品だと思っております。どういうことかというと、個人の収入や家庭の事情によって、投資に回すことのできる金額や期間、取れるリスクの度合いなどは、それぞれ異なっています。その点、デリバティブ、特にオプション取引は、多種多様な戦略を実現できる非常に便利なツールですので、個人の千差万別の資産形成ニーズや戦略に応じた投資戦略がとることができるわけです。
――投資家各々の事情やニーズに合致した多彩な手法や戦略を用いて、投資家が自らリスクを管理し、リターンの極大化をめざす。それがデリバティブの本質というわけですね? 上手に活用すれば、個人投資家にとっても強力な利器になりそうです。
「減らしたくない」日本の国民性にも
実はフィットしている!?
――ただ、そのためには、個人投資家サイドも緻密に勉強する必要がありますね。 特に投資を始めて日が浅い初心者は「どの銘柄が上がるのか」ばかりに関心が行きがち。改めて欧米並みの“投資教育”の必要性を感じるお話です。
巽 ご指摘のとおりですが、国民性もありますからね。
これまでの日本の文化では、どちらかといえば「資産を減らさない」ことが大事とされ、誉められてもきました。
これに対して欧米のキリスト教文化圏には、伝統的に「タラントンのたとえ」という考え方が定着しています。“タラントン”とは聖書に出てくる通貨の単位で、転じてタレント(才能)という言葉の語源にもなっているのですが、あるとき主人が三人の従僕に、それぞれ5タラントン、2タラントン、1タラントンを預けて旅に出る。前の二人は預かったお金を運用して2倍に増やし、戻ってきた主人に誉められますが、1タラントンを預かった最後の一人は「ご主人様の大切なお金を失ってはいけないので、土に埋めて保管しておきました」と言って、主人をがっかりさせてしまう。
「進んでリスクをとり、資産を活用することの必要を説いた教え」というわけで、日本の伝統的な価値観とは違っています。
――デリバティブは、やはり日本人には馴染みづらい?
巽 ただ、デリバティブとかオプション取引で「リスクを管理する」という考え方は、まさに「自分で決めたレベル以下には資産を減らさない」ということです。
確かに難しい側面はあるのですが、本質的には「減らさない取引」を志向しているのがデリバティブなので、きちんと戦略を立てて臨めば、本来、大きく損をすることはないはずなのです。損をするのは、他人からお金を借りて、身の丈に合わない投資をして失敗したときですね。
今の世の中、自ら積極的に株式を保有しようと思わなくても、相続などで株を持っている人が大勢います。そういう人は「大きく増やそうとは思わないが、絶対に損はしたくない」とお考えのはず。デリバティブは、実はそういう方々のニーズに適った取引といえます。
もっといえば「損失は限定させながら、利益はなるべく極大化したい」と考えるのは、ごく当たり前のことでしょう。
「ミニ先物」など、より小さな資金で始められる商品もありますから、初心者の方にもぜひ関心を持っていただきたいと思っています。
土本 『かぶオプ』を使えば、「減らさない」どころか、“塩漬け”になっている株式を有効活用することもできます。
 たとえば、過去に高値で買った株式を持ち続けて、塩漬けになっているような株式とそれに対応するコールオプションを組み合わせる「カバードコール」という投資手法を使えば、定期的にオプション売却代金を得るという戦略も検討できます。これは比較的リスクの低いデリバティブの利用方法です。
たとえば、過去に高値で買った株式を持ち続けて、塩漬けになっているような株式とそれに対応するコールオプションを組み合わせる「カバードコール」という投資手法を使えば、定期的にオプション売却代金を得るという戦略も検討できます。これは比較的リスクの低いデリバティブの利用方法です。
それから、特定の株への強い相場観をお持ちの投資家の方であれば、上昇・下落のどちらに対してもリスクを一定の範囲に抑えながら、株式を保有することなく、『かぶオプ』のみでその相場観に合わせた投資をすることが可能となります。
このようにオプション取引は、投資戦略の幅がものすごく広い分、個人投資家の方それぞれが本当に必要としている方針にあてはまるものを見つけられる可能性を秘めています。
とはいえ、こういったデリバティブの特性を正しく理解されている個人投資家は、まだまだ少ないと感じていますので、この度の統合というエポックを機に、さまざまな施策を通じて、しっかりと浸透を図っていきたいと考えています。